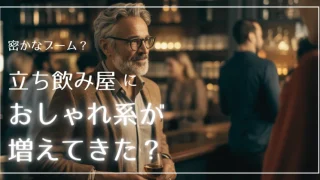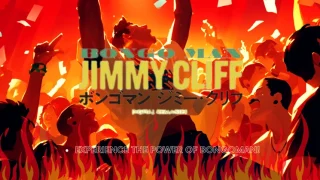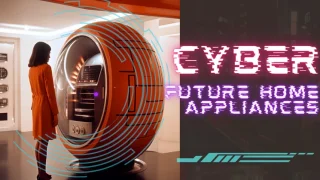「正人」の日記
「正人」の日記 読書感想:読後感想第一弾「ザリガニの鳴くところ」文庫本版。文庫本を待って損したゾイ! 今回の件から読書離れを考えてみた。
単行本が話題になっていたのは知っていた。
ただ話題になっているからと言ってボクの趣味範囲にあたるかどうかは別問題なので買うかどうかは逡巡していて結局単行本は買わずに文庫本になるのを待っていた。
文庫本になるまでに映画化されたのも後に知ることになったが、気が付けば観る機会を検討する間もなく終わってしまっていた。そんなこんなでようやく文庫本が出たところでようやく手に取ったわけである。