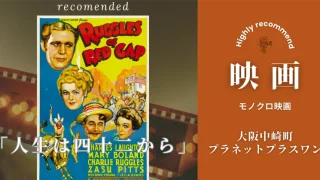 「正人」の日記
「正人」の日記 映画時評:モノクロ映画「人生は四十二から」を観た。大推薦! もし観ることが出来る環境があるなら是非!
大阪の中崎町にあるミニシアター、プラネットプラスワンでモノクロ映画「人生は四十二から」を観た。想像以上にムッチャ面白かった!
もし皆さんに見る機会があるなら大推薦だ!
「もし」と書いたのは、そもそもこの映画は1935年公開の米国映画。なかなか見る環境にある方は少ないだろう。
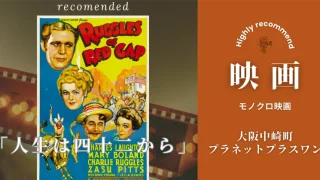 「正人」の日記
「正人」の日記  「正人」の日記
「正人」の日記  「正人」の日記
「正人」の日記 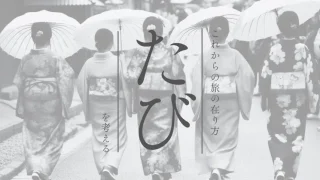 「正人」の日記
「正人」の日記  「正人」の日記
「正人」の日記  「正人」の日記
「正人」の日記 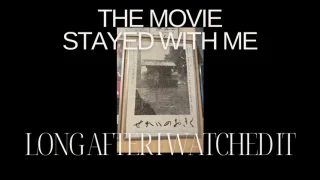 「正人」の日記
「正人」の日記 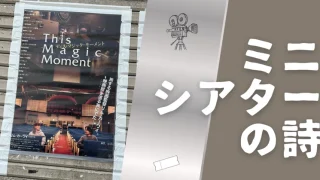 「正人」の日記
「正人」の日記 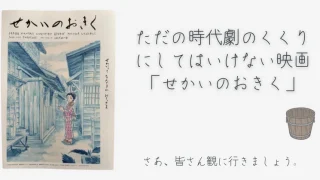 「正人」の日記
「正人」の日記 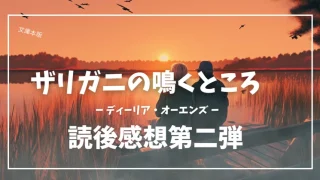 「正人」の日記
「正人」の日記